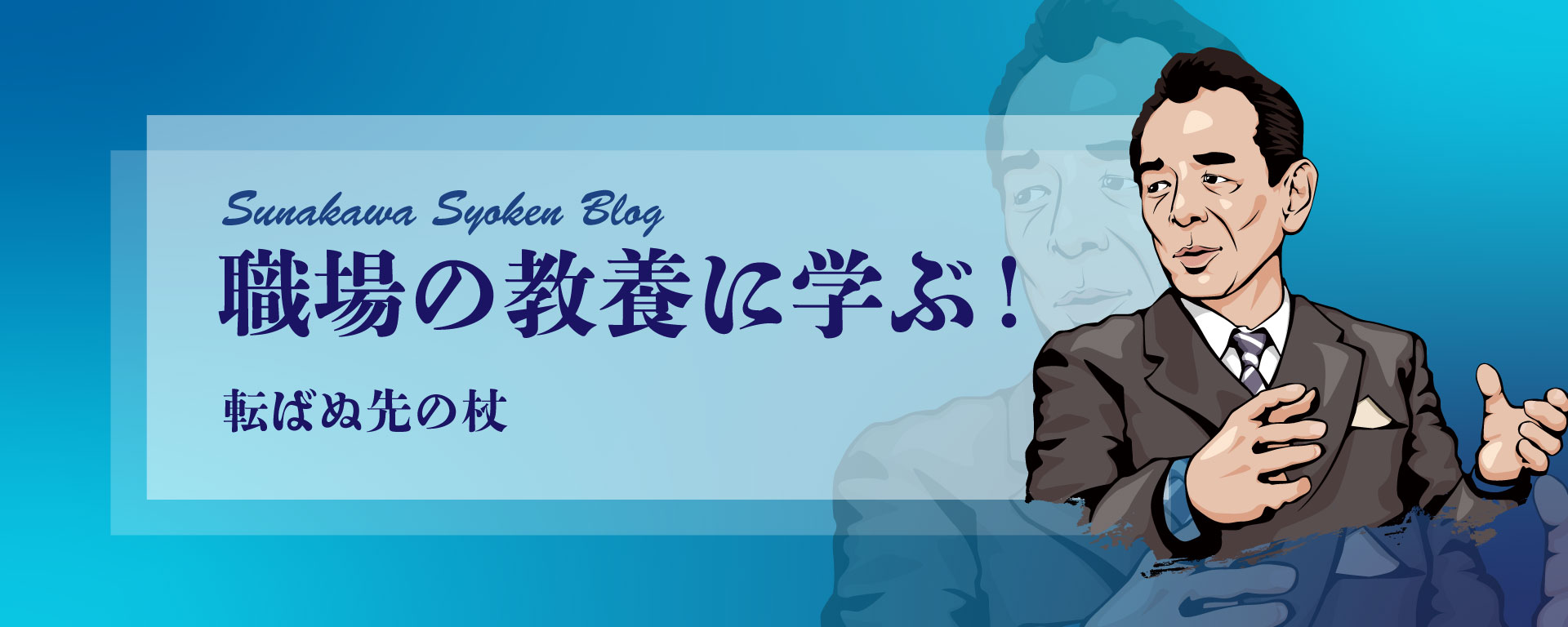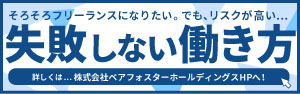《職場の教養に学ぶ》
お題:米百俵まつりとその精神
2025年10月4日(土曜)
【今日の心がけ】長期的な視点を持ちましょう
砂川昇建の思うところ
米百俵まつりとは、新潟県長岡市で毎年行われるお祭りです。背景には「米百俵の精神」と呼ばれる逸話があります。戊辰戦争後、長岡藩は困窮していました。そのとき支藩から「百俵の米」が送られます。人々は「飢えをしのぐために配ってほしい」と望みましたが、藩の大参事・小林虎三郎は、「今食べてしまえば一時しのぎ。これをもとに学校をつくり、将来の人材を育てよう」と決断しました。つまり、目の前の飢えを満たすのではなく、学びによる未来への投資を選んだのです。この精神を讃えて、長岡では「米百俵まつり」が開かれています。人間が「火を扱えるようになったこと」で他の動物より優位に立った例のように、 学びは単なる知識習得ではなく「生きる力の拡張」といえます。原始の学び:火を使う、道具を作る。生存の可能性を広げる。社会の学び:農耕、文字、制度をつくる。共同体を安定させる。現代の学び:科学、技術、哲学。生活を豊かにし、意味を探る。ここから見えてくる本質は、 学ぶことは「より良く生きる」ための技術と視野を広げること。つまり、学びは「学問」だけに閉じたものではなく、暮らしを便利にする ・困難に耐えられる力を育む・人と分かち合う基盤をつくる、といった、人生そのものを豊かにする営みでもあります。米百俵の精神は「目先の利益より、学びという未来の糧を優先する」姿勢を示し、学びの本質は「生き延びるだけでなく、よりよく生きるための力を生み出すこと」にあります。
著者 砂川昇建