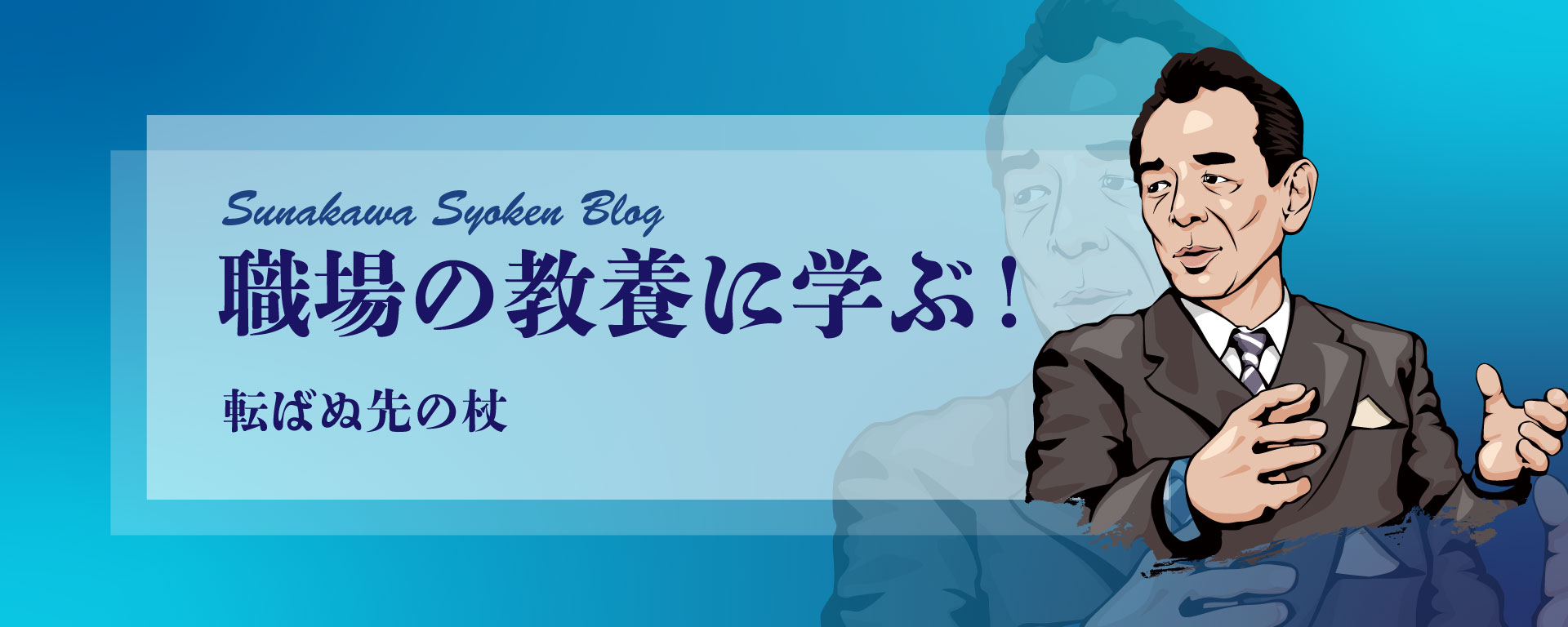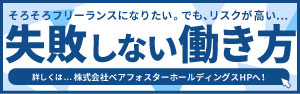《職場の教養に学ぶ》
お題:ゴミ拾い
2025年9月27日(土曜)
【今日の心がけ】公共意識を高めましょう
砂川昇建の思うところ
「ゴミを拾う」という一見ささやかな行為と、仏教の「悟り」の関係、そして周利槃特(しゅりはんどく)の故事をつなげてみましょう。ゴミを拾う行為と仏教的な意味。仏教では「行為(カルマ)」が心に影響を与え、修行や悟りの因縁を作ると説きます。ゴミを拾うことは単に環境をきれいにするだけではなく、次のような修行的意味があります。執着や我欲を離れる実践→ゴミを拾うとき、自分のためではなく「人や場所をきれいにしたい」という利他的な心が働きます。これは「布施行(ふせぎょう)」に通じ、心を清めます。心を整える瞑想的な行為→ゴミを拾うとき、ただ黙々と一つひとつ拾う行為は「作務(さむ)」に近く、雑念を減らし、心を今に集中させます。これは禅的な実践にもなります。因果の法則を体感する→一つ拾えば一つきれいになり、続ければ全体が清浄になる。小さな因(行為)が確実に果(結果)につながることを実感でき、仏教の基本原理を身で学べます。周利槃特は釈迦の弟子のひとりで、非常に物覚えが悪く、経文を覚えることもできなかったと伝えられています。あるとき釈迦は彼に、複雑な経文ではなく 「塵を払え、垢を除け」 という短い言葉を与えました。周利槃特は毎日その言葉を唱えながら、掃除を繰り返しました。最初は表面的に掃除をしていました。やがて「外の塵を払うことは、心の中の煩悩の塵を払うことでもある」と気づきます。掃除を通じて「心の清浄とは何か」を体得し、ついには悟りを開いたとされます。つまり、周利槃特は 「掃除」という日常の行為を、悟りの道に転換した」 のです。周利槃特のように、単純な掃除やゴミ拾いも、心のあり方次第で深い仏道実践になるわけですね。
著者 砂川昇建