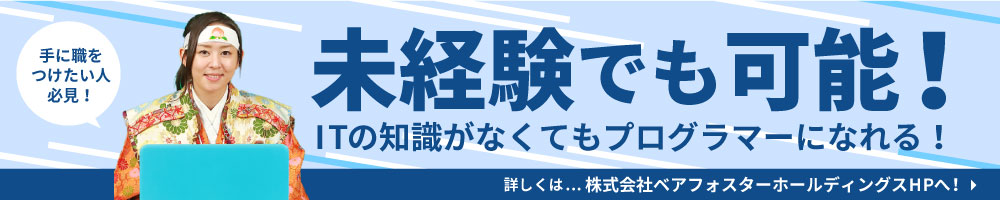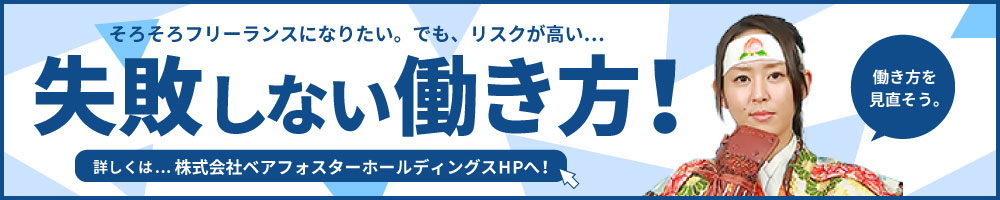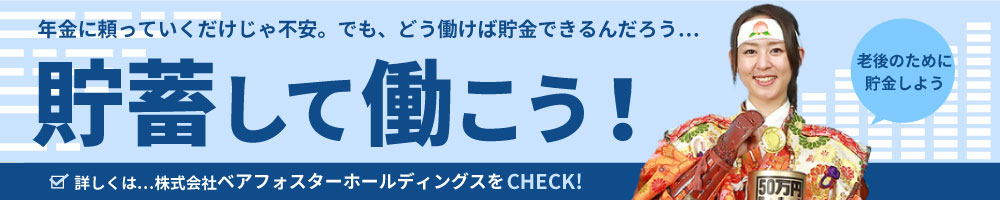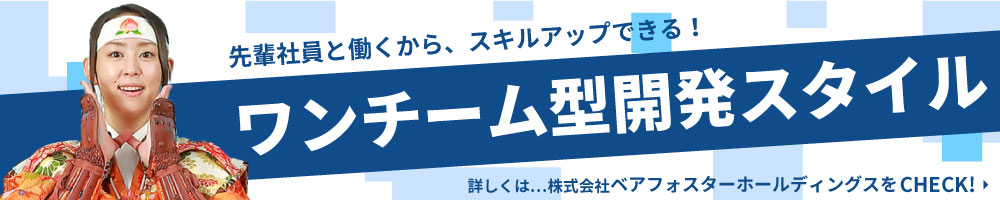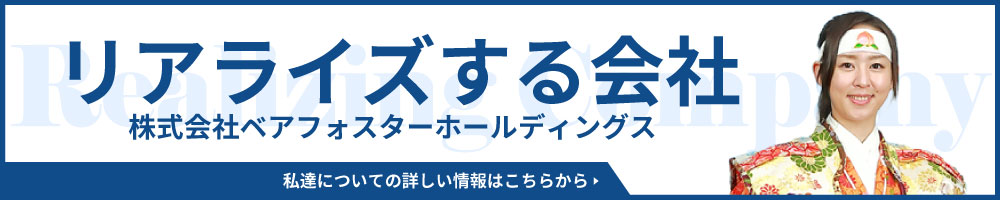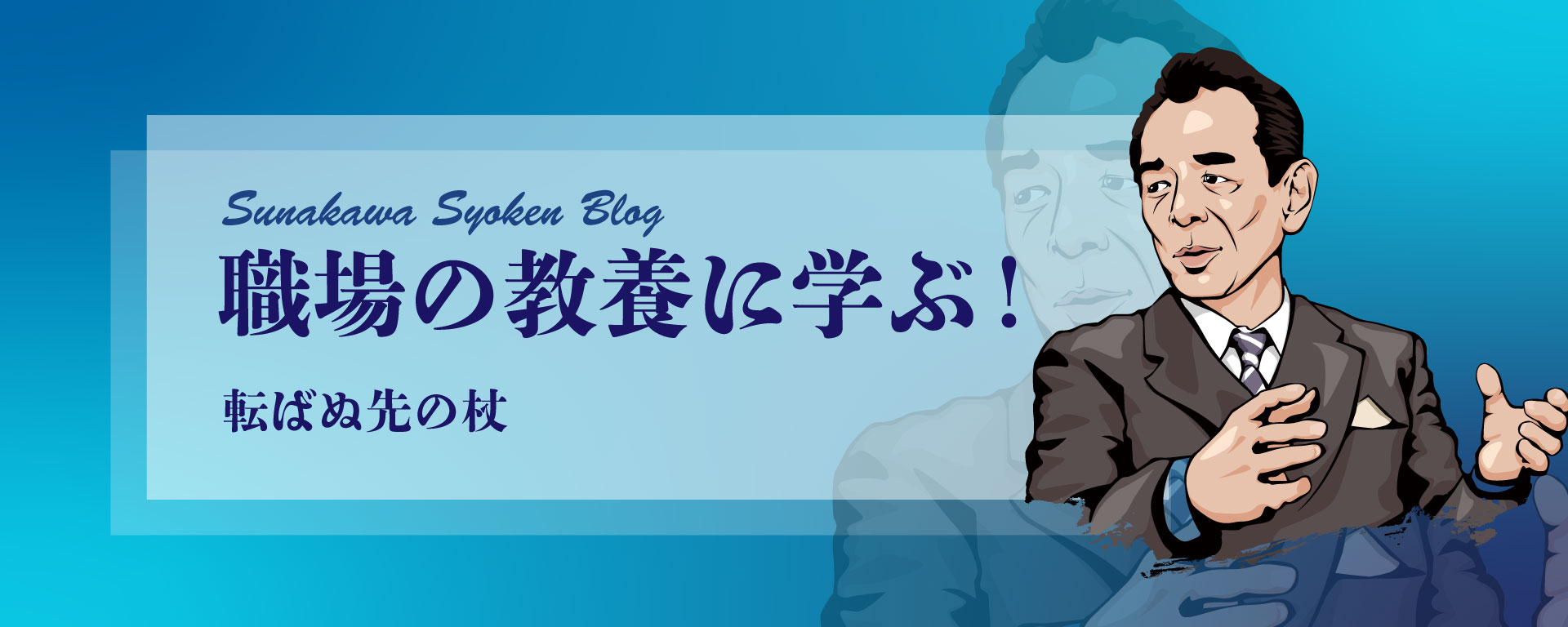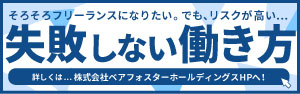《職場の教養に学ぶ》
お題:謝罪の言葉
2025年11月14日(金曜)
【今日の心がけ】相手の気持ちに寄り添いましょう
砂川昇建の思うところ
学校教育は、「褒めて育ててる」が基本になっています。ですから、最近の子は、自分の非を認めません。そして謝罪することができません。昭和は「馬鹿野郎」が基本ですから、謝罪が日常茶飯事です。「褒めて育てる」教育の功罪、そして「失敗を認められない社会」がどんな未来を招くか――これは現代日本社会にとって非常に重要な問いです。平成、令和は、「褒めて伸ばす」「失敗を責めない」が中心。しかし、結果として「間違いを指摘される=人格否定」と感じやすくなり、「失敗を認める」「謝罪する」ことが心理的に非常に難しくなっている。本来の自己肯定感は「失敗しても自分には価値がある」と理解すること。しかし、「間違えない=価値がある」と誤って学んだ場合、→ 失敗を認めると「自分の存在」まで否定されたと感じてしまう。「SNS世代」では「炎上」や「悪口」に敏感で、他者の批判に過剰反応する傾向。これにより、防衛的態度(自分を正当化する・言い訳する)が強くなりやすい。学校や家庭で「叱られる経験」「失敗を修正する経験」が減少。結果として「失敗後の正しい行動(反省・謝罪・改善)」のモデルを学ぶ機会が乏しい。職場→責任の所在が曖昧化し、トラブル対応が遅延する。失敗を共有できず、同じ過ちが繰り返される。組織→改善文化が衰退し、PDCAが「P止まり」になる。表面上の調和が保たれても、実質的な成長が止まる。人間関係→衝突を避ける「無責任な優しさ」が増える。信頼関係の構築が難しくなる。国家・社会→問題が発覚しても「責任回避」や「説明不足」が蔓延。結果的に社会全体の信頼度が低下。つまり、「謝罪できない社会」は「学ばない社会」に直結します。昭和の「叱って育てる」は厳しさで成長を促した。令和の「褒めて育てる」は安心で成長を促す。これから求められるのは「失敗を共に考え、共に成長する教育」です。謝罪できない社会は、一見平和でも、内側では学びが止まります。しかし、誤りを認め、互いに支え合う文化を再構築すれば、「優しさと強さを両立した社会」に進化できます。
著者 砂川昇建