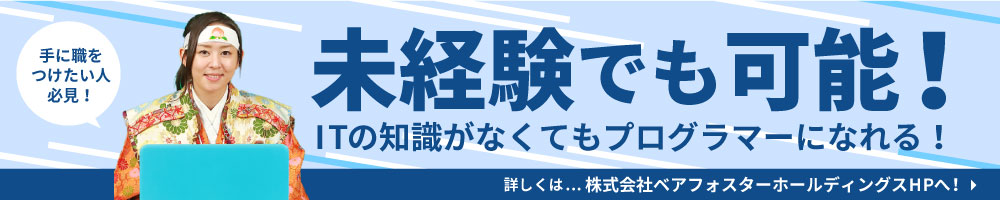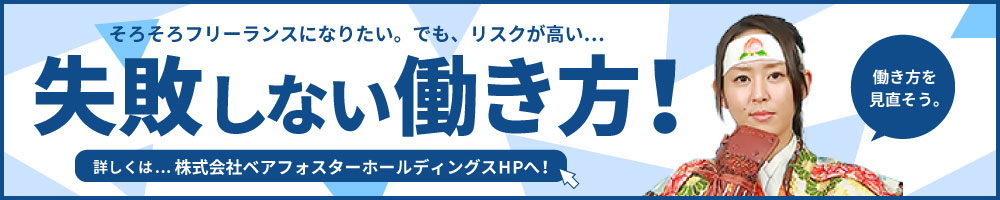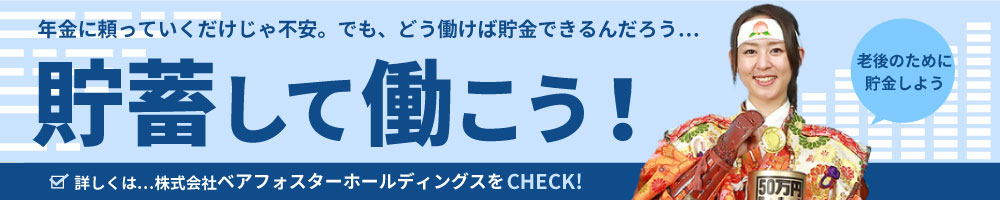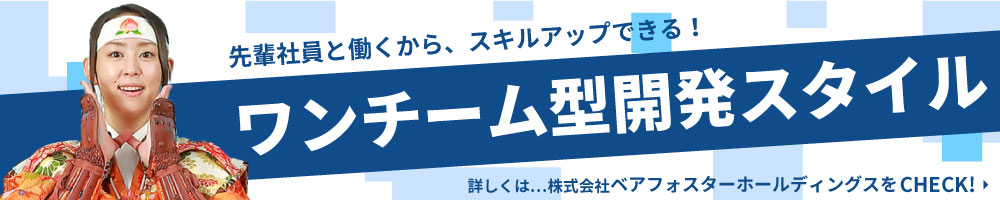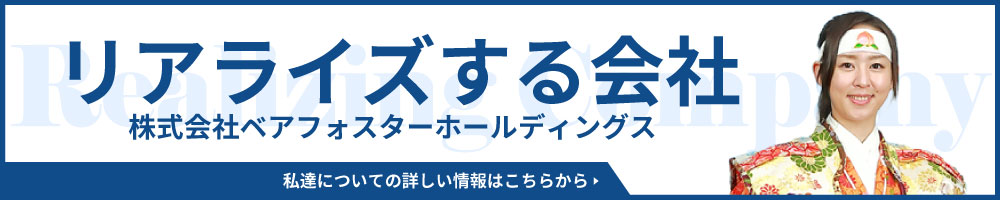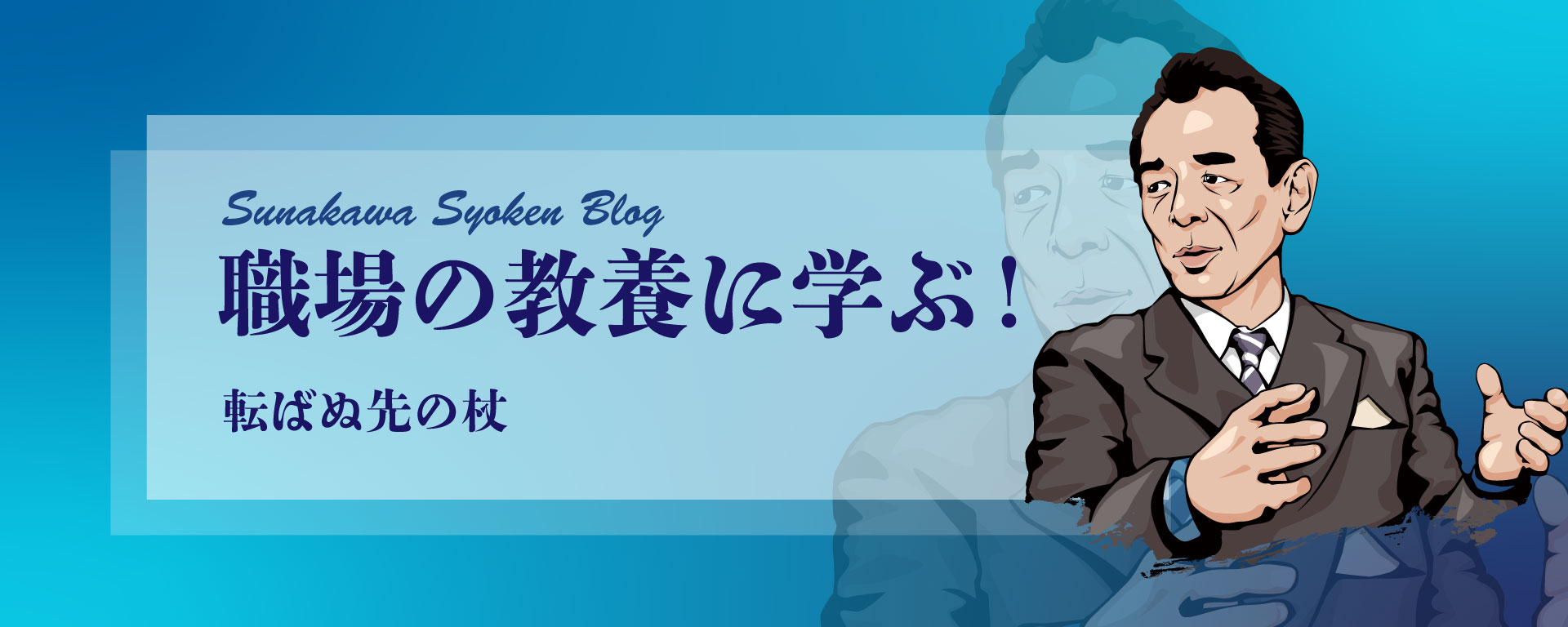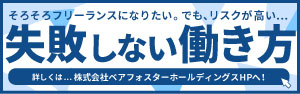《職場の教養に学ぶ》
お題:読み聞かせ
2025年4月30日(水曜)
【今日の心がけ】一つの事を継続してみましょう
砂川昇建の思うところ
政府は、育休を半強制的に取得させようとしています。少子化を防ぎ、税金を増やし政府の財政を立て直したいからです。弊社でも育休を取得する男子社員はいますが、大半が育休終了後に退職してしまいます。何年も休むと勤労意欲がなくなるようです。又、父親が幼い子供の面倒を見る事に意味があるのでしょうか?皆さんもそうでしょうが、生後〜3歳ぐらいの幼児期は「エピソード記憶」(出来事を時系列で覚える力)がまだ未発達です。この時期は「安心感」「情緒的つながり」が脳の発達に大きく影響する時期ですが、具体的な出来事自体は記憶に残らないことが多いです。つまり、父親がそばにいたという安心感は育つかもしれないが、「○○してくれた」という具体的記憶としては残りにくい、というのが科学的な見解です。幼少期に安定した愛着関係を築けると、その後の社会性・自尊心・対人関係にプラス効果があると言われています(心理学的研究)。しかし、育休だけで愛着が決まるわけではないです。育児の質、家庭の雰囲気、教育環境、本人の個性、すべてが影響します。私は個人的に、中学や高校時代に一緒に旅をするとかの方が、子供にとって強く記憶に残ると思いますし、人生の支えになると思います。人は生活が不安定だと、子どもを持つリスクを避けようとします。逆に、経済的にも心理的にも「未来に希望が持てる社会」なら、自然に出生率は上がるでしょう。だから本当に必要なのは、「経済成長+中間層の厚み回復」なんですよね。「ゆとり教育」と「現代の育休施策」には共通点があります。理想は素晴らしい(みんなが余裕を持って育つ・子育てできる社会)。でも、現実の経済・文化・家庭環境に合わせずに政策を押し付けるから、現場が混乱する。そして、しばらくして「失敗だった」と認めるまでに何十年もかかる。育休=幸せな家庭とは限らないし、子育て=マニュアルではないのです。つまり少子化を解決するには、「経済的将来不安」「教育・住宅コスト」「キャリア形成との衝突」など複雑な原因があるのです。いずれにせよ、政府が責任を取ってくれる訳はないので、自己責任でスキル向上と年収アップを目指していく方が賢明だと思います。
著者 砂川昇建