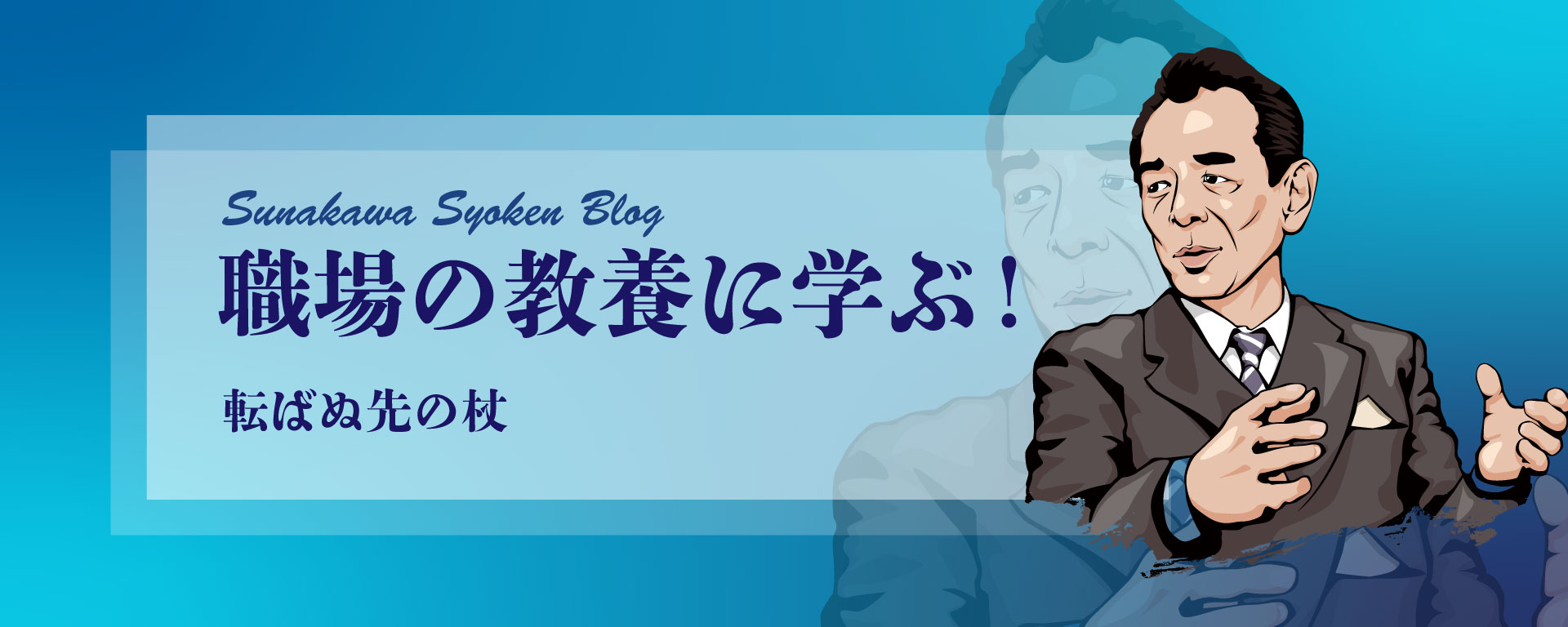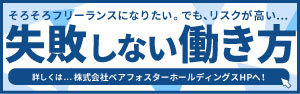《職場の教養に学ぶ》
お題:花を愛でる心
2025年10月1日(水曜)
【今日の心がけ】草花の命に目を向けて見ましょう
砂川昇建の思うところ
石垣島の施設では、ハイビスカスが沢山植えられています。ヤギの子供が大きくなって葉っぱを食べるようになると、ハイビスカスの花は咲きません。防衛本能でしょうか?また、雑草とりや肥料をあげるときれいな花が咲きます。物い言わぬ花ですが打たれれば響きます。ヤギに食べられると花が咲かないのはなぜ?ハイビスカスは葉がたくさん光合成をして、はじめて花を咲かせるエネルギーを蓄えられます。ヤギが葉を食べると、そのエネルギー源が失われるので、植物は「命をつなぐこと」を優先して花を咲かせる余裕をなくしてしまうんです。これは「防衛本能」というよりも、「限られた資源の中でどう生き延びるか」という戦略。生き物として、とても合理的な判断をしているといえます。雑草とりや肥料で花が咲くのはなぜ?雑草があると、土の中の栄養や水を奪い合ってしまい、ハイビスカスは十分に育ちません。肥料は、光合成だけではまかないきれない栄養を補ってくれます。環境が整うと、植物は「今なら子孫を残せる!」と判断し、美しい花を咲かせるのです。花が物語る「植物の素晴らしさ」と環境に応じて変わる柔軟さから学べます。花を咲かせるかどうかも含め、植物は常に周囲の条件を読み取り、最適な選択をします。「物言わぬ声」に耳を傾ける喜び、人間には聞こえないけれど、葉の色、花の数、茎の伸び方で「元気」や「困っている」を教えてくれます。共生の循環、花はただ美しいだけでなく、虫や鳥に蜜を与え、種を運んでもらい、命の循環をつなげています。人が少し世話をすれば、その分だけ応えてくれる。沈黙の中に深いコミュニケーションがあるのが植物の魅力だと思います。
著者 砂川昇建