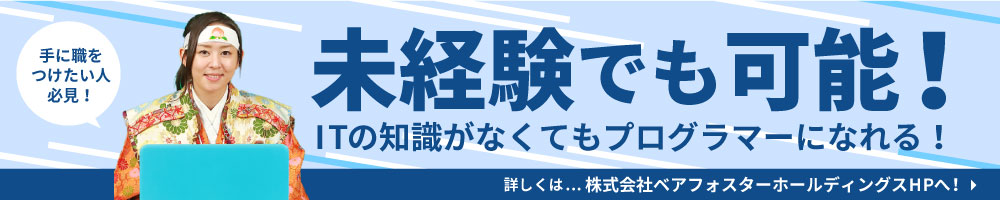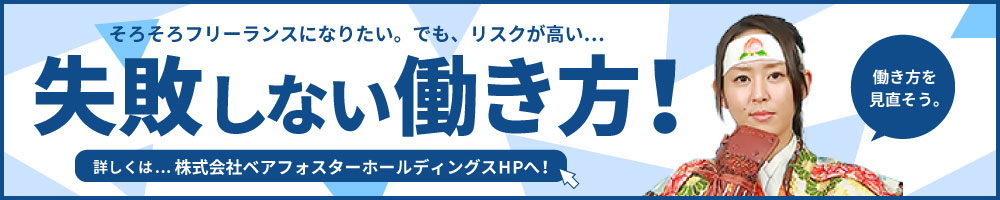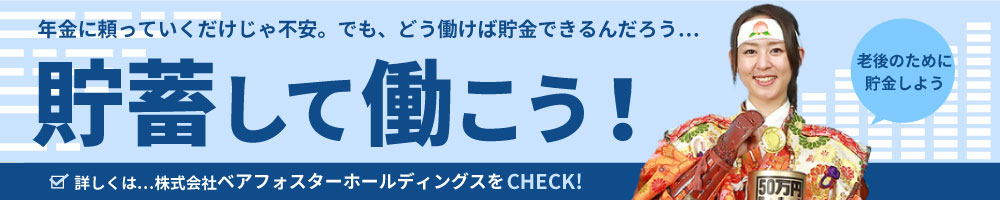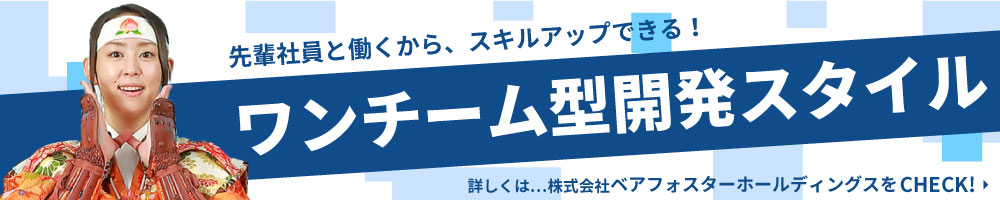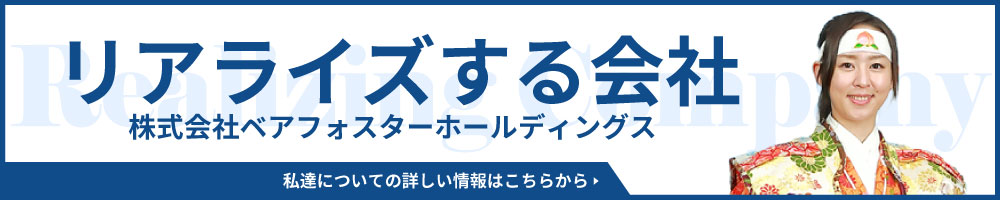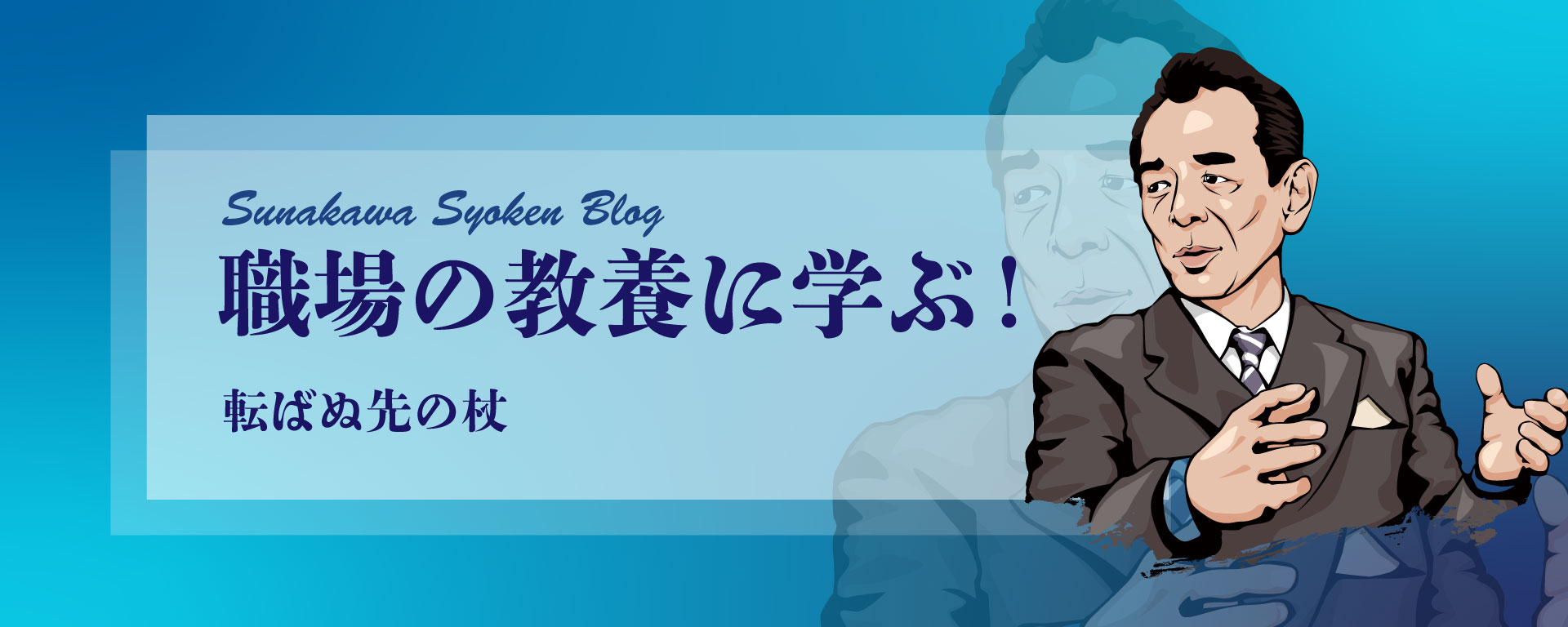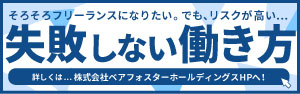《職場の教養に学ぶ》
お題:稲作の祭り
2025年5月3日(土曜)
【今日の心がけ】地域行事に興味を持ちましょう
砂川昇建の思うところ
田植えの手順です。春、温かくなる前に「育苗(いくびょう)」といって、種もみを水に浸して発芽させ、苗床で苗を育てます。苗が15〜20cmくらいに育ったら、田んぼに植え替えます(これが田植え)。昔ながらの農家さんは、自分たちで苗を作ることもあります。しかし現代では、専門業者(育苗業者)から「育った苗」を買う農家も多いです。理由は、労力削減・品質安定・作業時間短縮など。昔:ほぼ自家育苗。今:自家育苗もあるけど、市販苗を買う農家も増えた、という感じです。昔は完全に人力でした。一本一本、手で苗を植えていたんです。かがみっぱなしで何時間も作業するので、 腰を壊す人が続出、 「腰の曲がったお年寄り」が当たり前にいた、という背景がありました。現代は、田植え機(田植機)という機械を使います。6列とか8列とか同時に苗を植えられるので、作業スピードが圧倒的にアップ!お米と言えば、江戸時代の大名は石高で力の強弱が決まりました。1石(いっこく)は、成人男性1人が一年間食べるお米の量(約150kg)に相当。例えば「10万石の大名」なら、理論上、10万人の生活を支えられる。大名は、年貢でお米を集めていましたが、大名が自分ですべて食べるわけではありません。年貢米を市場に出して現金に換えていたのです!大坂(大阪)や江戸には「米市場(米会所)」があり、そこで米を売って→現金を得て→ 武士の給料(俸禄)を払ったり、城を修理したり、家臣を養ったりしました。米を売るルートを押さえることが、政治力=経済力=軍事力そのものだったので、大坂の米市場をコントロールすることは超重要でした。現代社会は、農協お米流通をかなりコントロールしています。そして確かに、それは江戸時代の大名と米市場の関係に「よく似た構造」があります!一時期は、お米は農協を通さなければいけない時期もありましたから、農協は、大名と同じだったんですね。農民のお祭りから始まり、お米の経済を勉強する事も大切ですね。
著者 砂川昇建