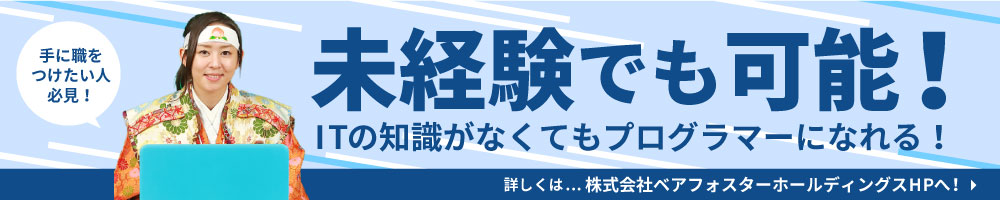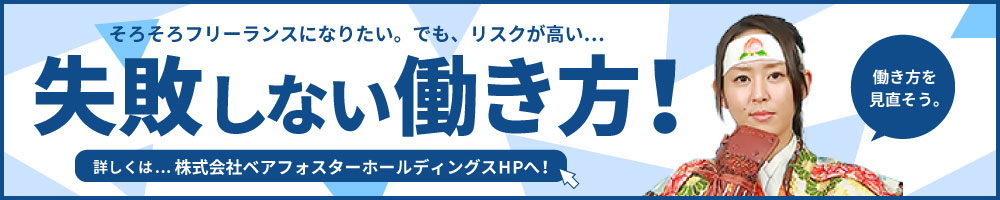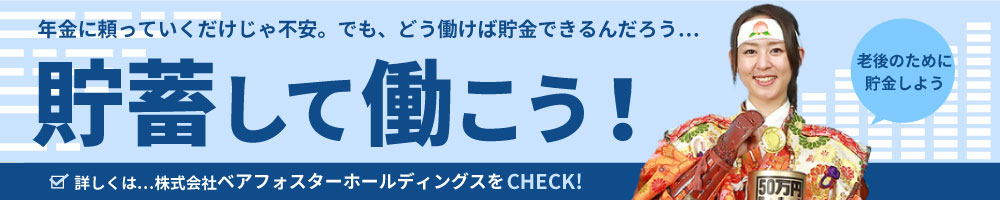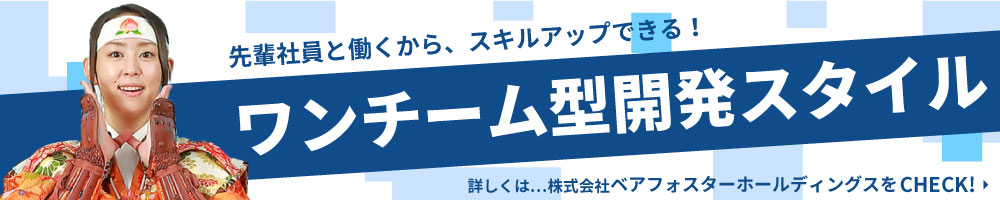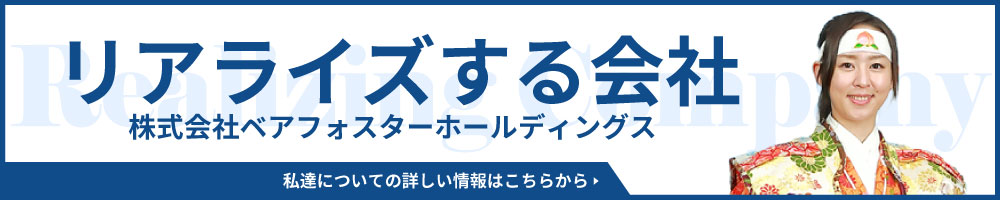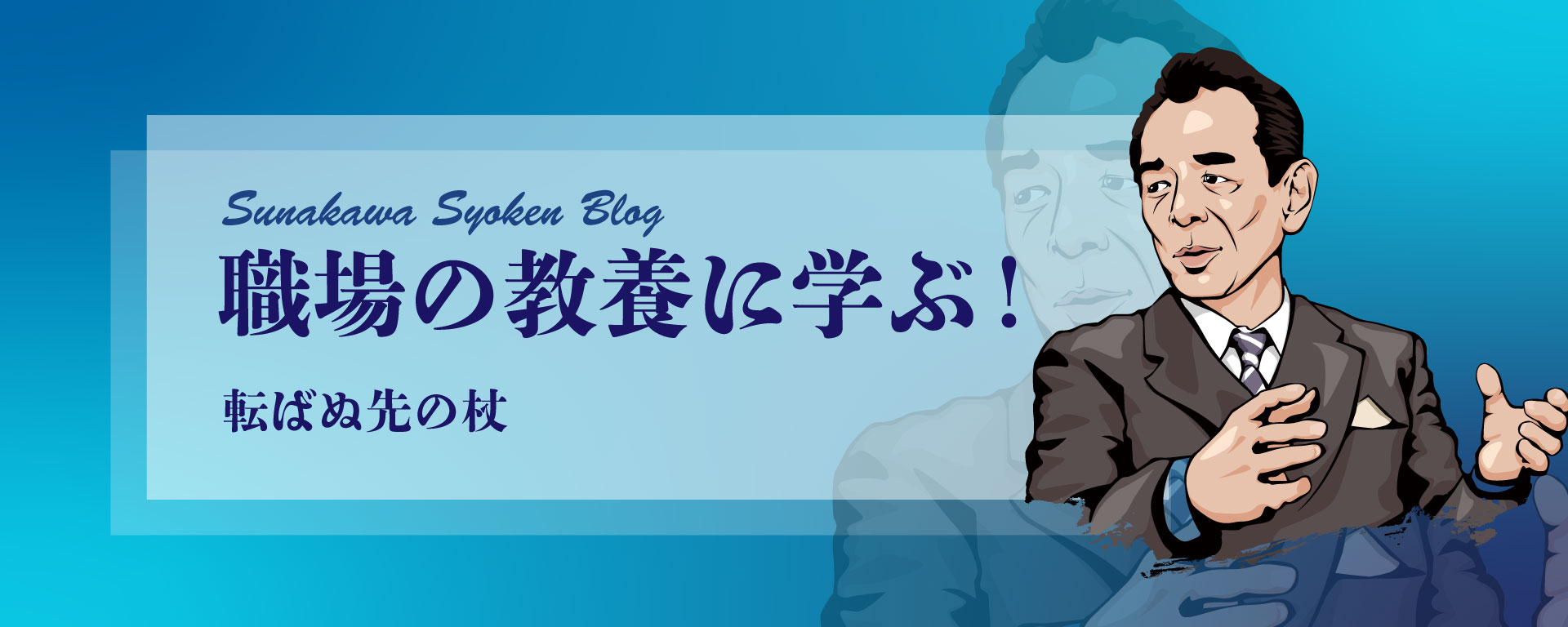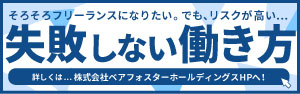《職場の教養に学ぶ》
お題:家族旅行
2025年1月30日(木曜)
【今日の心がけ】人と上手に付き合いましょう
砂川昇建の思うところ
妻の振る舞いに感謝する夫の話です。夫は反省するエピソードが多いのですが執筆者が妻なのか夫なのか気になります。このエピソードの中で「見返りがあるものだな」と言う言葉があります。仏教的な視点から「見返り」とは非常に興味深いテーマです。仏教の基本的な教えの一つに「無為自然(むいしぜん)」があります。これは、見返りを期待せずに、自然体で行為を行うことを意味します。たとえば、妻が店員と仲良く話したのは、おそらく純粋な心から来たものでしょう。結果として穴場を教えてもらったという「恩恵」が生じたとしても、それは意図したものではなく自然な結果です。仏教では、「カルマ(業)」という法則があります。善行は良い結果を生み、悪行は悪い結果を生むとされています。ただし、善行を行う際に見返りを求めてしまうと、その行動の純粋性が薄れると考えられます。つまり、仏教的には「見返りを求めない行動」こそが、最も深い意味で善いものとされるのです。仏教的な視点から「見返り」とは非常に興味深いテーマです。仏教では、行動や意図のあり方に深い関心があり、それが「見返り」という考え方にも影響を与えます。以下にその神髄についてお伝えします。 1. 「見返りを期待しない行動」の大切さ 仏教の基本的な教えの一つに「無為自然(むいしぜん)」があります。これは、見返りを期待せずに、自然体で行為を行うことを意味します。たとえば、妻が店員と仲良く話したのは、おそらく純粋な心から来たものでしょう。結果として穴場を教えてもらったという「恩恵」が生じたとしても、それは意図したものではなく自然な結果です。仏教では、「カルマ(業)」という法則があります。善行は良い結果を生み、悪行は悪い結果を生むとされています。ただし、善行を行う際に見返りを求めてしまうと、その行動の純粋性が薄れると考えられます。つまり、仏教的には「見返りを求めない行動」こそが、最も深い意味で善いものとされるのです。 2. 見返りの「自然な循環」 見返りそのものを否定するわけではありませんが、仏教ではそれを「自然の摂理」として受け入れる姿勢が大切です。たとえば、お釈迦様の教えにおいて「布施(ふせ)」という行為があります。これは、他者に物や助けを無償で与えることを指します。この布施は、見返りを期待するために行うのではなく、純粋な慈悲心や思いやりから生まれるものです。しかし、そうした布施が結果的に心の豊かさや周囲からの信頼をもたらすことがあります。これを仏教では「善因善果」と言います。妻の行動によって「穴場を教えてもらえた」というのも、因果の自然な循環の一環と考えることができます。つまり、善意が善意を呼び寄せたと言えるでしょう。仏教的な見返りの神髄は、「期待せずに行う行為が、結果として善い循環を生む」という考えにあります。妻が店員と話した結果穴場情報を得たという出来事は、自然な因果の流れであり、善意や思いやりの連鎖が引き起こしたものです。仏教の教えに従えば、「行動そのものを楽しむこと」や「他者への利他の心を育むこと」が、最も尊い見返りと言えるでしょう。 3. 「利他の精神」が本当の見返り 仏教では、真の幸福は「利他(りた)」の精神から生まれるとされています。「利他」とは、他者のために尽くすことです。しかし、その背景には「自他不二(じたふに)」という考え方があります。これは、自分と他人は切り離せない存在であり、他者の幸福が自分の幸福につながる、という考えです。つまり、見返りを意識せずに他者に優しく接したり、助けたりすることで、結果的に自分も幸福になれるという教えです。妻が店員と自然に話をし、店員もそれを嬉しく感じた結果として、穴場情報が得られたという流れも、この「利他と自他不二」の法則に通じるものがあります。仏教的には、見返りそのものよりも、行為そのものが大事とされます。行為を行う瞬間の心のあり方、プロセスにこそ価値があります。たとえば、妻が店員と話をする中で、互いに笑顔や親しみを共有したその瞬間こそが、仏教的な見返りの「神髄」と言えるでしょう。穴場情報という結果があったかどうかではなく、そのプロセスそのものが幸せを生む原点です。
著者 砂川昇建