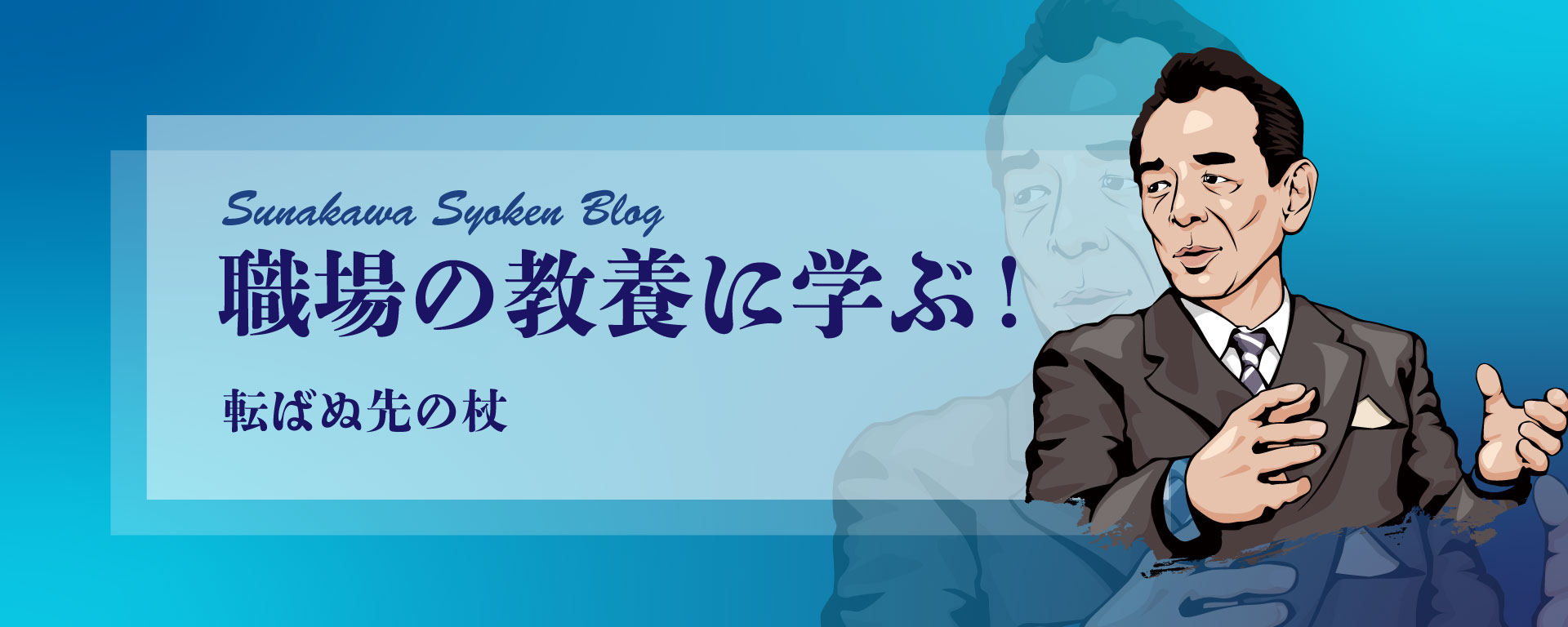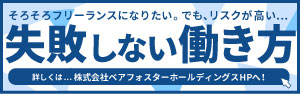《職場の教養に学ぶ》
お題:道理に従う
2025年8月29日(金曜)
【今日の心がけ】人生のモットーを見つけましょう
砂川昇建の思うところ
善悪二元論から「灰色」を受け入れる、事について考えてみたいと思います。学校教育は「答えがある世界」でしたが、社会は「答えがない問題」ばかりです。だからこそ、「正解を探す」のではなく、何故、そうなったのかを体験し考え受け入れる事が重要です。善悪や正義に固執するのではなく、「ここでできる最善は何か?」を考える姿勢が人生の智慧になります。ストア哲学的モットー→「自分にコントロールできることに集中し、できないことは受け入れる」組織の構造や上司の性格は変えられないけれど、自分の態度・努力・学び方は変えられる。受け入れることで無力感ではなく、逆に行動のエネルギーを自分の領域に集められます。禅的モットー→「置かれた場所で咲きなさい」どんな環境でも、まずは自分が貢献し結果を出すことを通じて存在価値を示す。すると周囲の景色や関係性も変わり、自分が改善できる立場に近づいていきます。実用的モットー→「正しさよりも、成果と信頼を積み重ねる」 「自分は正しい」と言っても、成果や信頼がなければ誰も耳を貸しません。一度でも結果を出せば、意見を通せる余地が生まれます。順応だけでは自分を失い、ただの「迎合」になってしまいます。主体性だけでは孤立してしまいます。大切なのは「環境に適応しつつ、自分の軸を少しずつ表現していく」ことです。まずは貢献し、成果で認められる。その上で小さく改善を試みる。徐々に自分の哲学を活かせる環境を広げていく。人生のモットーは一人ひとり違ってよいですが、社会でしなやかに生きる指針としては、「正しさに固執するよりも、最善を尽くして成果を出し、信頼を得る。その上で少しずつ世界を良くしていく」という姿勢が現実的で、かつ哲学的にも深みのあるモットーになると思います。レオン・フェスティンガーの理論によれば、人は「自分の行動」と「自分の信念」がズレると、心に不快感を覚えます。善悪や価値観は普遍的なようでいて、社会や文化が違えば大きく変わります。→ 考えだけに頼ると相対化に耐えられなくなるが、行動を通じて「相手や環境に合わせて調整する力」を養える。「自分の考えは絶対」ではなく、「やってみて考える」習慣がつく。結果として、変化の多い社会でも適応力が高くなる。書物や理屈で理解するより、実際の行動から得た体験は実感を伴う。その結果、より現実的で説得力のある価値観に変化していく。「真の正義」とは、頭の中で思い描いた理想ではなく、現実の中で実際に他者に役立ち、社会に機能する正義 のこと。行動を通じてこそ、机上の理想が「本当に役立つのか」自分の信念が「他者や社会にどう響くのか」を検証できる。「考えたら負け、行動しましょう」
著者 砂川昇建