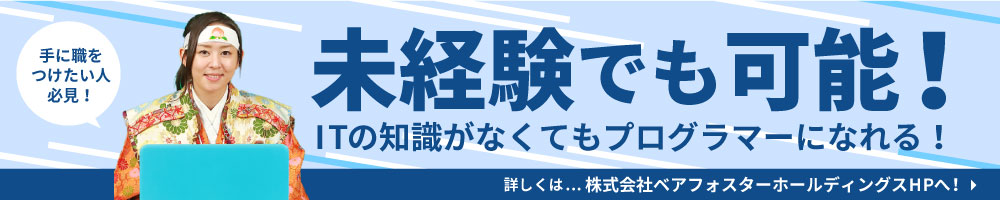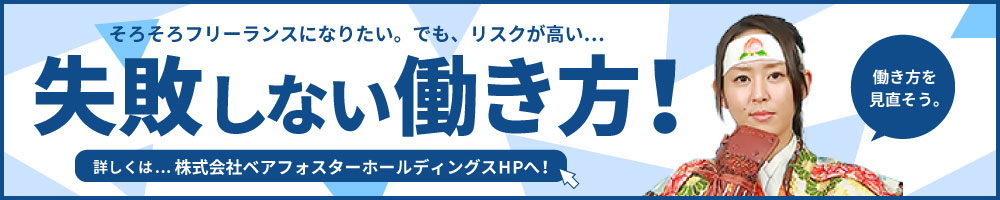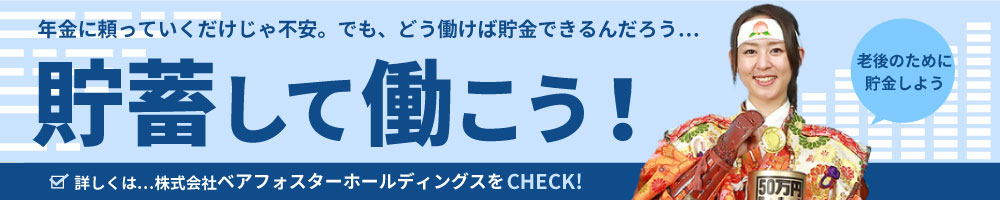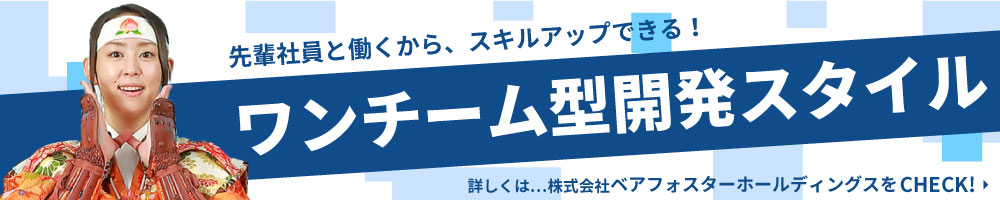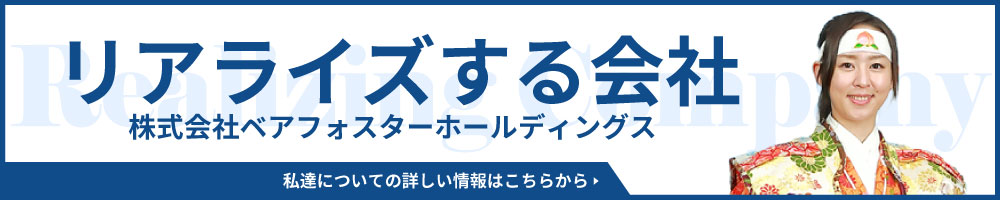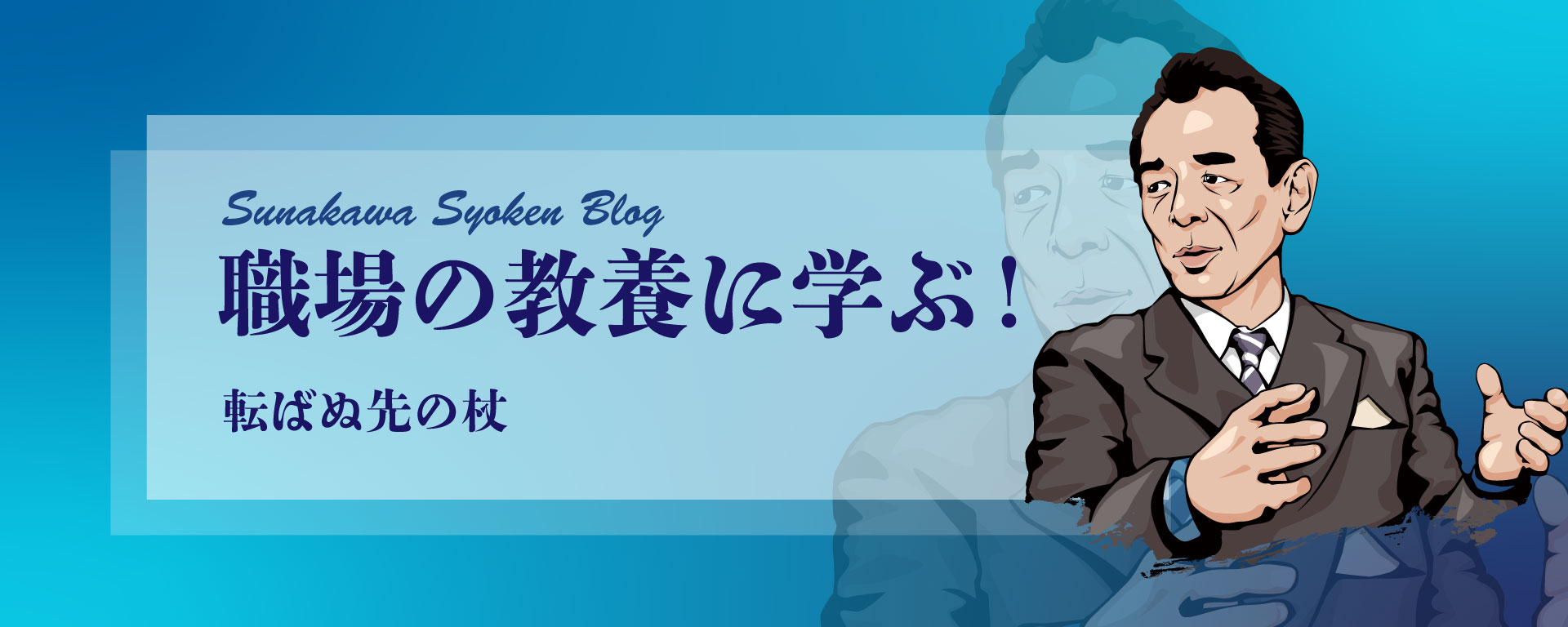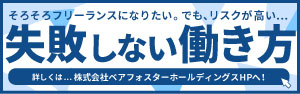《職場の教養に学ぶ》
お題:鬼は内
2025年2月3日(月曜)
【今日の心がけ】地域の伝統から学びましょう
砂川昇建の思うところ
節分(せつぶん)は、日本の伝統的な行事で、「季節の変わり目」に行われる厄払いの儀式です。特に現在では、**2月3日頃(立春の前日)**に行われることが一般的です。「節分」とはもともと**「季節を分ける日」**という意味。昔の日本では、春夏秋冬それぞれの始まり(立春・立夏・立秋・立冬)の前日を「節分」と呼んでいました。現在は特に立春の前日の節分が重要視されています。立春(2月4日頃)は、旧暦では一年の始まりとされる重要な日でした。新しい年を迎える前に、邪気(鬼)を払って清める儀式として、節分の行事が定着しました。節分といえば「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまくのが定番!昔の日本では、「豆」には魔(ま)を滅(め)する力があると考えられていました(語呂合わせ)。鬼(邪気)を追い払うために、大豆をまく風習が広まりました。炒った大豆(福豆)を用意する(生の豆は芽が出るため、縁起が悪いとされる)。恵方巻の風習は、もともと大阪発祥の商人の習慣だった。秋田県では、「ナマハゲ」が鬼の象徴として扱われることも。北海道や東北では、雪が多いため、豆まきに落花生を使う家庭も多い。節分は、日本の「厄払い」と「新しい年を迎える準備」の大切な行事。現代ではイベント要素が強まっているものの、「福を呼び込む」という本来の意味を大切にしたいですね!
著者 砂川昇建